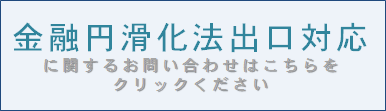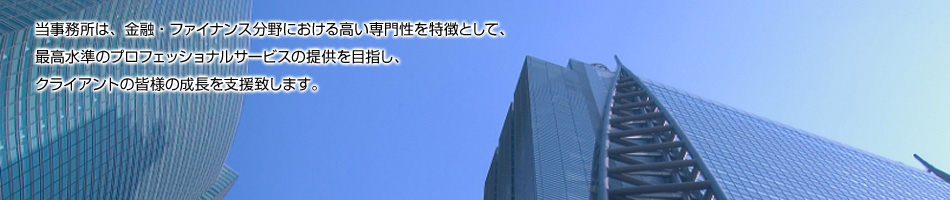DCF法の個別論点
株価評価においてDCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法の採用はかなり一般的なものとなっています。そのため、バリュエーション関連の教科書や参考書などでは、キャッシュフローの考え方にはじまり、割引率の計算方法、継続価値(ターミナルバリュー)の算出方法、などなど細かい論点を丁寧に説明しているものが多くなっています。
DCF法自体は、いわゆる金融工学的発想を背景として、その割引現在価値を算出するものであるから、かなりの仮定的要素や前提条件を盛り込んで算出することになります。従って、それら要素や前提条件が変われば算定結果も大きく変わることが良くあるのです。
そんな中で、教科書的にあまり深く説明されていない論点で、かつ筆者としても重要だと感じている論点を以下いくつか纏めてみました。
1.事業計画/プロジェクションそのものの評価と利用について
投資銀行などの外部算定者が株価評価を行う際に、会社から受領する事業計画について「会社が作成したものをそのまま採用しています」とした前提条件のもと、その後のプロジェクション策定や、価値評価に利用しているケースが多いです。
もちろん、会社策定の事業計画をそのまま採用することは基本的に正しいことであり、採用しないことを推奨するものではありません。しかしながら、この基本動作が専門家の対応として適切かはよく考える必要があるでしょう。すなわち、評価を実施する専門家として、いったん会社側の作成する事業計画につき自身の目線でリスク要素の加算や、アップサイド要因の検討など行い、何が事業計画の重要な変動要素になるかを独自に分析するプロセスを経る必要があるというものです。
近時の株価評価に係る裁判事例(いわゆる「公正な価格」についての価格決定)などを見ると、たとえ上場企業であっても、単純に市場株価に対してプレミアム○○%という株価決定は不適切と考える動きが強くまっています。近時においては、「企業価値の増加」を加味した価額、すなわちシナジー価格をもとに利害関係者に増分価値を適正配分すべきとして、DCF法を強く意識した判断を下しています。
もっとも現時点において、DCF法の前提となる事業計画数値については「高度な経営判断」のもとで採用されたとの理解を前提に、株主のみならず外部者がその妥当性や合理性を法的に追求する段階には達していないと思われます。しかしながら、算定書の外部開示が一般化しつつある近時においては、たとえサマリー部分であろうとも事業計画数値やプロジェクションが社外に開示される可能性は高まっています。そうすると、現実的でない事業計画やプロジェクションであることが結果として判明した場合に、「高度な経営判断」の妥当性や合理性についても遡及される懸念は、今後においてゼロではなくなります(ただし、ここまで厳格に責任追及をする動きはまだ明確になっていません)。
要するに、外部算定者が「会社が作成したものをそのまま採用しています」としたディスクレーマーを付すだけでは不十分になりつつあるといえます。また、責任やリスクという観点を除いても、バリュエーションに関するプロフェッショナルとして事業計画をしっかり分析する作業を省略するのは、手続き的に不十分(=プロとしての品質管理が出来ない)といえるでしょう。
もちろん、算定者による独自の検証や分析を行ったうえ、会社側と十分協議し、最終的に会社作成の事業計画をベースケースとして採用することは何ら問題ないですし、むしろそのようなプロセスを積極的に踏むべきと筆者は考えます。
2.割引率について
DCF法の基礎となるCAPMモデルほか各種財務モデルには、必ず割引率という概念が登場します。
そして、財務モデルに取り込むプロジェクションが厳格に各種変動要素であるとかリスク要因をきちんと織り込めない場合、「割引率」部分にそのリスク要因を織り込んで調整するとの説明がなされるケースがあります。確かに、不確実要素やリスク要因を割引率に加算するという考え方は合理的なものと思えます。
しかしながら、それではどの程度のリスク・プレミアムが割引率に追加されるべきかとの議論については細かい検証がないのが実態だと感じています。CAPMモデルにおける割引率(=WACC)という定義については、「資本コストと負債コストの加重平均値」という普遍的概念がありますが、その中に織り込むパーツについては、上述のリスク・プレミアム要素としていくつかの論点があると思われます。
以下は、筆者が感じる論点です。
① リスク・フリー・レート
一般的にもっとも信用力のある国債の利回りを採用しています。何年もの国債を利用するか(通常は10年物と思われる)、どのスワップレートを使うか、直近レートか一定期間平均レートかなどの細かい論点もありますが、近時の国際金融市場(とりわけ欧州)におけるソブリン・リスクを考慮するロジックは見当たらないようです。
例えば日本国債は、他国のソブリン問題を受けてグローバルな資金流入が日本国債へと続き、異常なまでの低利になっています(2012年8月現在)が、この状況下における国債利回りをリスク・フリー・レートに採用すると資本コスト全体への影響が非常に大きくなる状況です。他方、過去数年間の平均のレートを採用する考え方もありますが、明確な基準は今のところなさそうです。
*10年もの国債の金利水準変動(過去3年推移)

要するに、このようなソブリンリスクなどの不確実要素が入り込んだ割引率にて求められたDCF評価が本当に信頼しうるものなのかは、多少の疑念があるところです。株式市場全体でPBRが1倍割れする株価の現状とを対比させると、「単に、DCF法評価には市場株価に反映されない将来価値が織り込まれている、現行株価より評価額は高くなる」との説明が果たして合理的なものかは何ともいえな気がします。
こういった不確実性要素を含む割引率を、さらにセンシティビティ分析を用いて価値変動割合を見ることになるのですが、いずれにしてもDCF法による株価レンジの上限と下限を求めるのは、バリュエーション実務者においてもかなり頭を悩ますところだといえます。
②小規模リスクプレミアム、非流動性ディスカウント
ひとことでいうと、割引率を調整する調味料のようなものですが、WACCという非常にロジカルな仕組みにいきなり主観的要素を持ち込んでしまう懸念もあります。
確かに、小規模リスクプレミアムにつき、「規模の小さい企業ほど市場における評価は低くなるから、割引率もリスクプレミアムが加算されている(ハズ)」との説明はそれなりに説得力があります。しかしながら、いくらのプレミアムが妥当かについての実証研究などは明確にないのが現状でしょう。米国における実証研究の結果を当てはめることも実務では行われていますが、かなり苦しい対応といわざるを得ません。
また、非流動性ディスカウントにおいても、非上場会社のように市場取引がなされない株式は流動性が低い(当然)から、それに見合うディスカウントを織り込むべきと説明されており、それなりに合理的な説明ともいえます。しかしながら、いくらのディスカウントを織り込むべきかについては、「IPO時の公開株価は市場株価の70%程度を予定している」などの説明にて、だいたい20-30%のディスカウントが妥当とする考え方か一般に認知されるのみが現状だといえます。
このように、WACC計算の前半までは非常に細かくコンマ%のレベルまで追い求めたにも拘わらず、小規模リスクプレミアムだとか、非流動性ディスカウントなどを(筆者的にはかなり大雑把に)加算することでWACC計算後半の結果を大きく変えてしまうケースが見られます。
********
上記の他にも様々な論点がありますが、それらは一般の教科書や参考書に譲ることにします。いずれにしても、DCF法には突っ込みどころが多々ある、非常に主観的要素が強い算定方法であることは間違いないといえます。
従って、バリュエーション専門家としては、最新の事情(判例動向、金融動向、その他)を敏感に受け止め、それらを取捨選択しつつ正しい株価評価を行うことが必要と思われます。
以上
サービスコンテンツTopへ